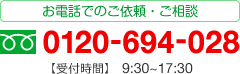外構工事の雑草対策で幅広く使われる防草シート・砂利の工事について解説します。コストパフォーマンスが高く、種類も豊富な人気の雑草対策工事ですが、仕上がりの美しさや長く安心して使うためには、見えない下地づくりが欠かせません。
防草シート・砂利の特徴や種類、工事手順、お手入れ方法など、工事前にも知っておきたい防草シート・砂利に関する知識を詳しくご紹介します。
防草シートとは?

防草シートとは、雑草を防ぐことを目的とした厚みのあるシートです。黒や濃い緑色の不織布が一般的で、外構部分に防草シートを敷くことで地面の光を遮り土地の中にある雑草の光合成を阻むことで発芽を抑制します。もちろん地面に敷くものですので透水性があり、水たまりの心配はありません。
防草シートの構造は大きく「不織布タイプ」と「織布タイプ」の2種類に分かれ、それぞれ異なる特徴を持っています。素材にはポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステルなどがあり、なかでもポリエステルは耐久性に優れているのが特長です。防草シートにはメーカーや種類によってさまざまな特徴や価格帯があり、選び方ひとつで仕上がりや耐久性が大きく変わります。敷設する場所の環境や用途に合った防草シートを選ぶことで、雑草対策の効果をしっかり発揮できるだけでなく、外構費用を抑えながら長く快適にお使いいただけます。
ガーデンプラスでは、お客様のご要望や設置場所の条件に合わせて最適な防草シートをご提案いたしますので、ぜひ安心してご相談ください。
不織布タイプ

不織布タイプの防草シートは、繊維を織らずにランダムに絡み合わせて熱や化学的な作用で結合したシートで、繊維同士のすき間が小さいため強度が均一なのが特長です。密度の違いによって価格帯も幅広く、マスクやフェルトなどにも使われる素材として知られています。
メーカーや製品により異なりますが、耐用年数は一般的に2~10年ほどとされており、しっかり選べば長期間雑草を防ぐことが可能です。ガーデンプラスでは、雑草の突き破りが少なく耐久性に優れた不織布タイプの防草シートをおすすめしております。
織布タイプ

織布タイプの防草シートは、その名の通り繊維を縦糸と横糸に織り合わせて作られたシートで、繊維同士のすき間が大きいのが特徴です。不織布タイプに比べると比較的リーズナブルな製品が多く、コストを抑えて雑草対策をしたい方に適しています。メーカーや製品により異なりますが、耐用年数は一般的に1〜5年程度とされており、短期的な雑草対策や一時的な利用におすすめです。
砂利・砕石とは?

砂利・砕石とは直径約数センチ程度の石のことで、狭義では一般的に角がなく丸い状態のものを「砂利」、大きな岩を砕いたような尖った形状のものを「砕石」と呼びます。
庭や犬走りなどの表面に敷き詰めるものは砂利と呼ばれることが多いですが、丸みを帯びている分、縁がない場所では歩行や雨などで砂利が流出してしまう可能性があります。一方の砕石は、角ばっていて、摩擦の力でその場に留まりやすくなります。重さのある車が行き来する駐車スペースでは、砕石を使用することが多いです。
砕石は土木用語で「バラス」とも言います。砂利や砕石を敷くことで、雑草の成長を抑制し、抜きやすくなるなどのメリットがあります。砂利や砕石は大きさの種類や色味が豊富ですので、ご自宅の外観やお庭のイメージによってお好きな砂利をお選びいただけます。
砂利敷きの適正な厚みは何センチ?
人が歩く場所

砂利の厚みは3㎝~5cm程が目安です。粒の小さな砂利であれば、薄すぎなければ防草シートが露出する心配はほとんどありません。ただし、これ以上砂利を厚く敷きすぎると歩行時に足元が不安定になり、転倒の原因になることもあるため注意が必要です。
駐車スペース

砂利の厚み5cm前後が目安です。粒の大きな砂利を使用する場合は、小粒の砂利に比べて防草シートが透けて見えやすくなるため、シートをしっかり隠すにはより厚めに敷きならす必要があります。車重が非常に重いために駐車場の砂利が移動してしまいやすく、タイヤで砂利を跳ね飛ばしてしまうことも多いため、歩行用よりは分厚く砂利を敷きます。
防草シート・砂利の相乗効果

雑草対策の方法として挙げられる防草シートと砂利敷き。外構工事では、この2つを組み合わせることで相乗的な効果を発揮します。砂利を敷くことで、防草シートの劣化を早める直射日光を防ぎ、また風などでのめくり上がりを防止します。砂利だけでは、雑草の発生自体を抑制することはできませんが、防草シートと組み合わせることで雑草の発生を防ぎ、また万が一発生した場合でも、容易に除去することができます。また、防草シートを敷くことで砂利の沈み込みを防ぎ、砂利の安定性が長く保たれます。ガーデンプラスでは雑草にお困りの方に防草シートと砂利敷きの組み合わせをおすすめしています。
砂利の下の防草シートは必要?

砂利敷き工事の防草シートは必須ではありませんが、併用しない場合はかなり雑草が生えやすくなります。防草シートを敷いていれば年に数回の手入れで済むところ、防草シートなしでは毎月、場合によっては数週間ごとの除草が必要になることもあります。防草シートは日光を遮り、雑草の発芽や成長を抑える効果があるため、砂利の下に敷くことで雑草対策の効果を大きく高められます。
どんなところに工事するの?
防草シートや砂利は、主に犬走りと境界の間のスペースやウッドデッキの床下など比較的目につきにくい場所から、庭やアプローチまわりなど幅広い場所で使用されます。目立たない外構箇所には砂利を使用し、正面の目に触れる場所には色味が豊富な化粧砂利を使用することでコスト面とデザイン面のバランスを取ることができます。
防草シート・砂利敷きの工事手順

❶ 地面を平坦に整地する
砂利の流出を防ぎ、歩きやすくするため、防草シートや砂利を敷き詰める場合は地面を整地します。また砂利によってかさ上げされる表面を周囲の高さと合わせたり、雑草の根や種子を除去したりするため、土の鋤取り(除去)を行う場合もございます。

❷ 防草シートを敷く
ロール状に巻かれた防草シートを敷いていきます。お庭には雨水桝やガスなど様々な蓋や管が出ています。それらの形に合わせて防草シートを切り抜きながら敷き詰めていきます。防草シート同士のつなぎ目は、しっかりと重ねて工事することが大切です。多くの防草シートは、雑草の侵入を防ぐために十分な重ね幅を取ることが推奨されています。防草シートは固定するため鉄製の杭(ピン)を防草シートの端・継ぎ目などに打ち込んでいきます。

❸ 砂利・砕石を敷き詰める
防草シートの上から砂利を敷き詰めていきます。道路側に面した場所ではトラックから砂利をそのまま運び入れることもできますが、庭の多くは車が入れないため、主に人力で砂利を運び入れていきます。砂利はレーキと呼ばれる大きな熊手で均一に敷き詰めます。砂利の量が少ないと防草シートが紫外線により劣化してしまうため、砂利の種類や場所によって変わりますが、十分に厚みを持たせます。
工事期間中、一部電動工具の使用や清掃等のため、電気や水道をお客様宅からお借りすることが一般的です。電気が使用できない場合は発電機を使用して対応しますが、その場合は大きな音が生じます。
防草シート・砂利の掃除について

雑草が生えた場合は手で抜いてください
防草シートと砂利を敷き詰めても、100%の雑草を防ぐものではありません。防草シートをカットした隙間や防草シートを突き破って生えてくる雑草もわずかですが発生することがあります。また、砂利の上に生える雑草は、風で運ばれた種が落ちて発芽する「飛来種子」が原因です。とはいえ、防草シートと砂利を敷いておけば根が深く張らないため、雑草が生えても手で簡単に取り除くことができます。発見した際は、こまめに手で抜き取ってください。
砂利や砕石が減ってきたら補充をおすすめします
砂利や砕石は雨や歩行などで敷地外に流れ出てしまうことがあります。砂利や砕石が減り続け、防草シートがむき出しになると紫外線によりシートの劣化を早める原因になります。工事直後に比べて砂利が減ってきたと感じたら、早めの補充をおすすめします。長く美しい状態を保つためにも、定期的な砂利の追加は大切です。補充の際には、最初に使用した砂利の種類を記録しておくと、補充の作業がスムーズです。