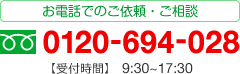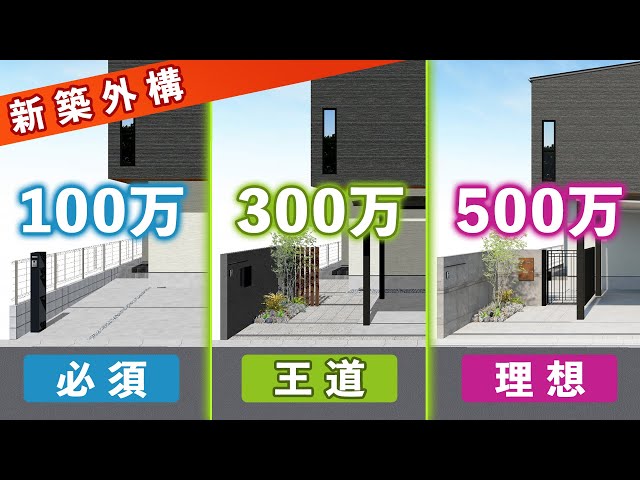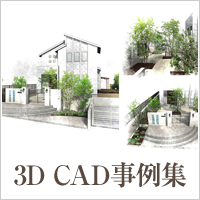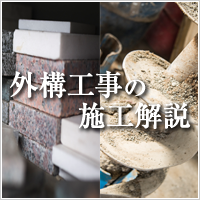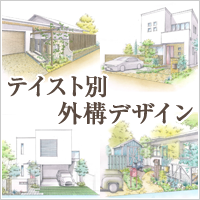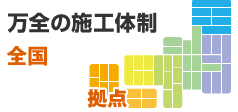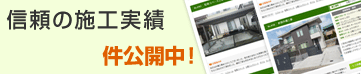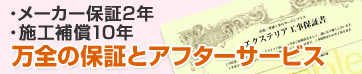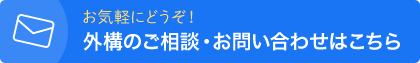お庭で万葉の風情を味わう「秋の七草」
万葉集でもたくさん詠まれてきた「秋の七草」を、お庭で育てる際のポイントと共にご紹介いたします。
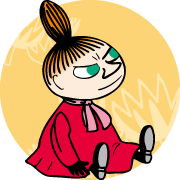
こんにちは、ガーデンプラスの中川です。
皆様は「秋の七草」をご存じでしょうか?「春の七草」は、「七草粥」などに代表される縁起物としてよくお店にも並びますが、秋にも奈良時代から代表的な七種の植物が「秋の七草」として選ばれています。春の七草が食用できるのに対し、秋の七草は今が見頃の観賞用植物が多いのが特徴。また園芸品種も作られているので、お庭で秋を感じたい方にもおすすめです。今回のブログでは日本の秋を彩る、「秋の七草」をご紹介いたします。
秋の七草とは
奈良時代の歌人・山上憶良が詠んだ和歌に「秋の七草」が選定されています。
秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり) かき数ふれば 七種(ななくさ)の花
萩の花(はぎのはな) 尾花葛花(おばな・くずばな) 撫子の花(なでしこのはな)
女郎花(おみなえし) また藤袴(ふじばかま) 朝貌(あさがお)の花
どれも秋に見頃を迎える花や草木ですが、「朝貌(あさがお)の花」は桔梗であるというのが現在の定説です。古くから愛されている植物は美しさを観賞するだけでなく、漢方や生薬の材料として、また建築物などの材料としても用いられ、日本人に親しまれてきました。
それでは、一種類ずつご紹介してまいります。
お月見に供えるススキ
秋の七草の代表格がススキ。ふわふわとした穂が実った稲のように見えるため、稲作の感謝祭であるお月見のお供えにも使われます。実はお月見の日は稲の収穫時期より早いため、すすきが代わりに使われたとか。昔は河原でも群生しているのがよく見かけられましたが、乾燥よりもやや湿り気を好む湿生植物です。
お庭に植えるには、大きくなりすぎないように注意が必要。鉢植えにしたり、根本を樹脂製の波板などで囲うと根が成長するのを防げるので、お庭でも楽しむことができます。またススキの中でも、イトススキやシマススキなどコンパクトな園芸品種ならおすすめです。
毎年新枝を出すハギ
マメ科で丸みのある葉と紫の可愛らしい花が特徴のハギ。万葉集でも最も登場回数の多い花で、赤みのある花にちなんで、お彼岸のあんこもちは「おはぎ」と呼ばれるようになりました(春のお彼岸のあんこもちは花盛りの牡丹にちなんで「ぼたもち)と呼びます)。日本ではいくつかの品種が自生していますが、最も広くお庭で育てられているのは、宮城地方でよく自生している「ミヤギノハギ」です。
マメ科の植物は根粒菌という、根っこにすむ菌と共生しています。作付け前の畑に、クローバーやレンゲを緑肥として植えるのは有名ですね。そのため、日当たりと水はけさえ良ければ、根粒菌が植物に必要な栄養分を作ってくれるので良く育ちます。ハギももちろんお庭で育てられます。冬は地上部が枯れるため、古い枝はばっさりと剪定してください。春にはまた株元から新しい枝が伸びてきます。
女性らしい姿で目を引き付けるオミナエシ
レースのような優しい黄色い小さな花を咲かせるオミナエシ。背もやや高く、風にそよぐワイルドフラワーの風情が美しい品種です。お庭でもよく育ちます。女郎花という漢字があてられることもありますが、名前の由来は「オミナ(女)」+「ヘシ(圧し)」で、他の女性を圧倒するほど美しいという誉め言葉です。
お庭でも日当たりが良ければよく育ち、晩夏から秋に明るい黄色い花を咲かせてくれます。多年草ですが種でも増やせます。背の高い植物と合わせると、中景としてうまく間をつないでくれそうです。
漢方や和菓子の原料となるクズ
漢方の「葛根湯」や和菓子の「葛餅」など、食用・薬用として用いられてきた歴史もある、馴染み深い植物。ハギと同じマメ科の植物ですが、つる性で、花は穂のように立ち上がりながら咲きます。一年で10メートルも伸びるといわれるほど成長が早いため、雑草化してしまうことも。あまりお庭向きの植物ではありません。
葛餅や葛湯の材料となる「葛粉」は葛の根から取り出されたでんぷんを乾燥させたもの。最近では国産の葛粉の製造が難しくなっているため、コーンスターチやサツマイモ由来のデンプンなどを混ぜることも多いそうです。葛の根には体を温める効果があるので、しょうがを入れた葛湯は肌寒くなってくる秋にぴったりですね。
家紋としても有名なキキョウ
濃紺や白い星形の花びらが美しいキキョウ。花開く前のふっくらしたつぼみも観賞価値が高い植物です。家紋に使われていることも多く、明智光秀の水色桔梗紋は有名です。実は野生のキキョウは絶滅危惧種に指定されていて、野山で出会えたら貴重です。
野生ではなかなかお目にかかれない桔梗ですが、美しい立ち姿から園芸品種は多く作出されていて、八重咲や絞りの入ったキキョウもあります。関東以西ではお庭でも多年草として育てられます。コンパクトなので和風の寄せ植えにもぴったりですね。
香りが蝶を呼ぶフジバカマ
糸のような細い花弁の花が咲くフジバカマ。繊細な見た目のほか、香りの良さでも愛されてきました。地下茎で増えるため本来は群生するような品種なのですが、実はこちらも現代の日本では絶滅危惧種で貴重な植物です。
お庭で育てるなら姿の良く似たセイヨウフジバカマ(青色フジバカマ)などが入手しやすくておすすめ。多年草で、晩夏~秋頃が開花期です。冬には地上部が枯れてしまいますが、初夏のころにまた芽吹きだします。
凛とした姿は日本女性のシンボル・ナデシコ
「大和撫子」という言葉がある通り、可憐な姿が愛されるナデシコの花。カーネーションやカスミソウも実はナデシコの仲間で、数多くの品種があります。日本に自生するのはカワラナデシコという深い切れ込みの入った花びらの品種で、凛とした風情を感じます。
園芸品種も多く作出されていて、開花期が長いものや四季咲き(環境さえ合えば季節を問わず繰り返し咲く)のものもあります。洋風のお庭に合う花も多いです。
こうしてみると、人々が川の近くに住み、身近な河原や湿地に自生していた植物が親しまれてきたことが分かります。護岸工事によって数はもちろんのこと、育ちやすい場所が少なくなってしまい、昔は誰しもが目にしていた植物が絶滅危惧種になってしまったなんて、和歌の詠み手も想像できなかったことでしょう。
お庭のために作られた園芸品種は山野に植えることは禁じられています。しかし、お庭で植物を育てることは蝶や鳥といった小さな生き物の生態系を守ることにつながり、間接的に野山の植物たちの営みを助けることにつながります。お庭で過ごす時間が増えたこの秋は、ぜひ「秋の七草」をはじめとした、身近な花や草に目を向けてみてください。

些細なことでも大歓迎!お気軽にお問い合わせください
お庭に関する事なら、ガーデンプラスへお任せください。ガーデンプラスは、全国で外構工事を手掛けるガーデンメーカーです。店舗でのご相談はもちろん、フォームやお電話からのお問い合わせも承っております。
記事に関してのご質問は、外構のプロスタッフがお答えいたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。洋風なお庭もカラフルでいいですが、和の植物も魅力的。日本の気候に合うものも多いので、花の少ない時期に上手に取り入れてみてください。
ガーデンプラス本部
Web担当
中川知春
お客様の目線に立って、お庭の楽しみ方や情報をお伝えしていきたいと思います。