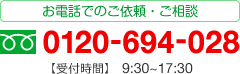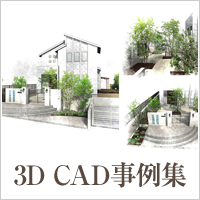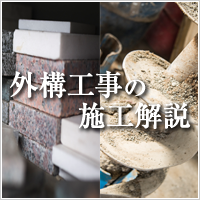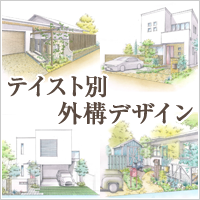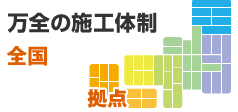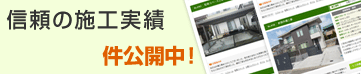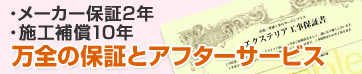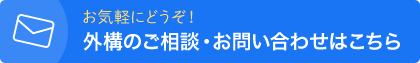日本の伝統美・ハナショウブ
古典園芸植物・ハナショウブを、お庭でも育ててみませんか?

こんにちは、ガーデンプラスの中川です。
今回は今が植え時のハナショウブをご紹介します。どれも日本ならではの美を感じさせる凛とした姿の花で、日本各所に自生しているところも見られます。
ハナショウブとよく似た植物に、アヤメとカキツバタがあげられます。「いずれアヤメかカキツバタ」という慣用句がありますが、優劣をつけがたいという意味と「見分けにくい」という意味でも使われます。今回はアヤメ・ハナショウブ・カキツバタの花の見分け方と、特に日本で愛されてきた古典園芸品種・ハナショウブについてご紹介します。
アヤメ・ハナショウブ・カキツバタの見分け方
まずはよく似た3つの花の見分け方をご紹介します。
アヤメ/花の付け根に「網目(文目)」模様が入っていることから、アヤメと呼ばれるようになりました。開花期は3つの中で最も早く、5月中旬から下旬ごろ。草丈は20cm~50cmほどと小ぶりです。日本の気候では、日当たりのよい乾いた場所に自生することができます。アヤメも古くからある植物なのですが、他の2つほど園芸品種としての交配は進みませんでした。
ハナショウブ/端午の節句で使われるショウブ(サトイモ科)とはまた別の品種なので、ハナショウブと呼ばれます。葉のかたちが本来のショウブによく似ていたことから同じ名前で呼ばれるようになったようです。花の付け根には黄色い筋が入り、草丈は50~100cmとやや大型。開花期は6月~7月頃です。最も適した生息場所は湿地。特に花を咲かせる時期は水分が必要になるため、花菖蒲園に行くと、開花期は修景効果も兼ねて根元に浅い水が張られていることもあります。開花期以外は水に浸からせずに管理します。
カキツバタ/花の付け根に白い筋が入り、草丈は50~80cm。開花期はアヤメとハナショウブの中間ぐらいで、5月中旬~6月中旬ごろ。こちらは浅瀬に生息する抽水性植物なので、年間を通して睡蓮鉢やビオトープなどに株を沈めて管理します。1株でももちろん美しいのですが、群生させても青い花の印象は薄れず、特に琳派の代表的絵師である尾形光琳が描いた「燕子花図(かきつばたず)」は国宝のひとつとなっています。」
そのほか、アヤメ科には花の付け根に黄色い帯が入るダッチアイリスや、大型で豪華なジャーマンアイリスなど海外生まれの品種も多いので、まずは育てる場所から選び、そして花の姿で好みのものを探してみるといいでしょう。
アヤメ、ハナショウブ、カキツバタはどれも開花後に種ができますが、基本的には株分けをして増やしていきます。種撒きの場合、撒いてから開花するほど株が充実するまでに3年ほどかかりますが、割と交配がしやすい種類のため、これまでに様々な品種が作られてきました。3つの花の中で最も育種が盛んなのはハナショウブ。実は日本の園芸史の中でも一大勢力となるカテゴリで、全国にも花菖蒲園がたくさんあります。それではハナショウブについて少しご紹介してまいります。
古典園芸品種の粋を極めるハナショウブ
ツツジやツバキ、キク、朝顔など、江戸時代以前から日本の愛好家の中で競って交配が進められた花や木は「古典園芸品種」と呼ばれており、ハナショウブとカキツバタも古典園芸品種です。また江戸幕府の将軍たちが、代々花が好きだったこともあって、珍しい花・美しい花を目上の方へ献上する風習が広まり、武士の家では園芸は教養のひとつとしてたしなまれるようになりました。特に「菖翁」と呼ばれた松平定朝は300品種もの花菖蒲をつくって天皇にも献上し、門外不出にすることを条件に他の藩の武士たちにも株を譲ったことから、各地の武士階級の間でハナショウブの育成が盛んになりました。
アヤメ科アヤメ属の花は、青や紫、白、桃色を基調とした色のバリエーションのほか、外側に垂れ下がる「外花弁」が特徴的ですね。ハナショウブやカキツバタでは、外花弁の数により「三英花」、「六英花」と呼び分けており、さらに花びらの多い八重咲もあります。花弁が縮緬状になっているもの、柔らかく枝垂れるもの、すっきりと勢いを失わないもの、波打つものなど様々なかたちが展開されてきました。また剣をイメージさせる葉の濃さや勢いも重要で、花だけでなく全体的なバランスの良さを鑑賞したい植物です。
系統は大きく分けて「江戸系」「肥後系」「伊勢系」「長井古種・原種系」と4つに分類されています。
庭に植えて群生を楽しみ、凛とした雰囲気の「江戸系」。ハナショウブ栽培の祖であり、江戸住まいだった菖翁の流れを組む、スタンダードな品種が多いです。花菖蒲園でもよく育てられているほど丈夫で増やしやすく、また「ハナショウブらしい美しさ」を感じられます。
室内に飾って楽しめるように、花の豪華さが喜ばれた「肥後系」。特に肥後藩ではツバキやハナショウブも育種家の会が作られて、門外不出として厳格に管理されました。八重咲や色のグラデーションなど花の姿もバリエーション豊富で、茶会のように花菖蒲を鑑賞するための作法もあります。
同じく室内で楽しむ目的ながらも女性らしい優しい雰囲気が賞賛された伊勢系。外花弁は3枚で垂れ下がったものが好まれました。淡い藤色やピンクのたおやかな姿が印象的です。
そして江戸時代には発見されずに、明治時代に公園となった長井市の地で発見された原種に近い「長井古種」。山野草の風情を残し、丈夫で群生向きなので花菖蒲園でもよく育てられています。
それぞれ理想とする花の姿が系統ごとに現れていて、園芸家の情熱と伝統の重みを感じます。明治以降は原種の新たな発見や海外でも交配が進みつつも、菖翁が作出した「菖翁花」をはじめ昔ながらの古風な風情の品種も保存されています。
原種に近い長井古種や、庭植えで楽しむのを目的とした江戸系には初めての方でも育てやすい品種が多いです。
伝統の花・ハナショウブをお庭に
ハナショウブは庭植えでも育てられますが、あまりスペースに余裕がないときは鉢植えでの管理もおすすめです。またポイントは開花期の水分。水切れするとしおれてしまうので、鉢よりもひとまわり大きくて深さのある受け皿に水を貯めて、水切れを起こさないようにするとよいですね。
実はハナショウブは開花期があまり長くありません。1つの花が2~3日程度しか持たず、1つの茎には2~3個の花が咲くので、1つの品種だと観賞期が一週間程度です。そこで、花ショウブの中でも開花期の早い早生種、開花の遅い晩生種をいくつか揃えて、次々と花が咲く様子を楽しむのがおすすめ。最近では増やしやすさ・育てやすさに着目した品種も新たに作られていますので、初めての方は丈夫な品種を選ぶとよいでしょう。
植え付け時はちょうど花が終わる7月頃からです。花と株の充実のために年3回ほどしっかり肥料をやる程度で、あとは普通の園芸用土特別な管理は必要ありません。冬には自然と葉が落ちますが、春になると新芽を出します。病害虫も少なく、ヨトウムシやメイガといったスタンダードな虫に注意する程度です。
5月終わりごろから7月ぐらいまでは花菖蒲園で開花株を販売しているところもありますので、お気に入りの株を見つけてみてはいかがでしょうか。
観賞期間はやや短いもののハナショウブは特に和の雰囲気があり、美しく涼しげです。
カキツバタと合わせ、江戸時代から続く伝統の園芸品種にぜひチャレンジしてみてください。

些細なことでも大歓迎!お気軽にお問い合わせください
お庭に関する事なら、ガーデンプラスへお任せください。ガーデンプラスは、全国で外構工事を手掛けるガーデンメーカーです。店舗でのご相談はもちろん、フォームやお電話からのお問い合わせも承っております。
記事に関してのご質問は、外構のプロスタッフがお答えいたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。昔から育てられてきた花や木は日本の気候に合って育てやすく、美しさも日本人好みのものが多いです。ぜひチャレンジしてみてください。
ガーデンプラス本部
Web担当
中川知春
お客様の目線に立って、お庭の楽しみ方や情報をお伝えしていきたいと思います。